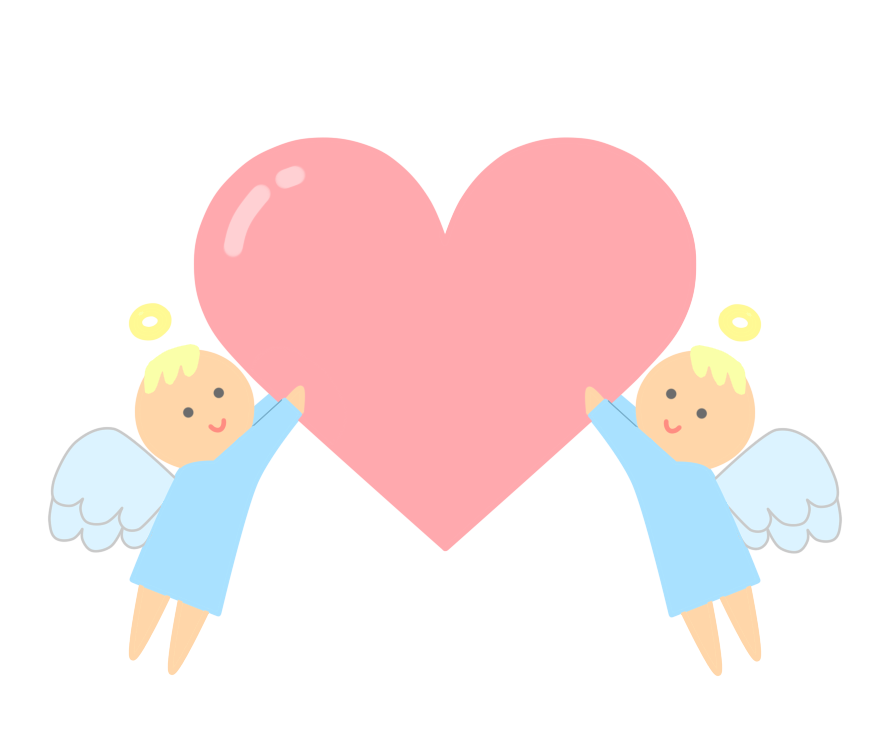
第五十二章 最高の思い出を君に届ける 二話
それから六年後。
理亜は豪真と結婚していた。
子供にも恵まれ、三歳の男の子が要る。
名前は神崎彰。
彰は人懐っこく、とても愛くるしい笑みが特徴だった。
「彰。こっちおいで」
「ママ~」
理亜もすっかり大人っぽくなり、髪も伸ばしていた。
彰は理亜の呼びかけに満面の笑みでよちよち歩きして近付いていく。
今いる場所は、砂川市立体育館の外のバスケットコート。
彰はまだ重いバスケットボールを両手にして抱きかかえる様に理亜に手渡す。
理亜は慈しみながら彰からボールを受け取ると、明人が「バスケもママも大好き」と拙い言葉で口にすると、理亜は益々、彰が愛おしくなり「後は君に任した」と笑顔で両手の拳を彰の前に突き出す様に差し出すと、彰も満面の笑みで両手の拳を作り、その小さな拳を理亜の拳とくっつける。
理亜はバスケを引退していて、学校を卒業後は、プログラマーとして、在宅ワークの仕事をしていた。
誰よりも心残りはあるが、家庭を築く事を優先した理亜。
だからこそ、バスケを託したいと言う思いが、息子の彰に向いてしまったのだ。
彰も、そんな理亜を見て「ママ~。見ててね」と笑みで口にすると、理亜からボールを持らってドリブルし始めたが、すぐに手から零れてしまい、コロコロとボールは転がる。
それでも彰は泣かず、一生懸命に健気に練習する。
そんな彰に近付いて優しく抱きしめる理亜。
理亜は警察署に居る明人との面会で、毎回の様に心が疲弊でもするかのように疲れ切っていた。
無理もない。
母親と明人の真実を知り、母親である郁美は他界し、スフィアとして、人を殺害し続けていた実の弟と毎日の様に対面しては、明人の身を案じ、申し訳ない気持ちを抱いていたのだから。
それからして、明人はウェルナー症候群の症状が悪化し、更に体が老体していった。
理亜が、高校を卒業する前に、最後に会った明人は、九十歳に見えるくらい老けていて、刑務所で老衰して、郁美の後でも追うかの様に、この世を去った。
唯一の肉親を失い、泣き崩れた理亜を、懸命に励まし続け支えてきた豪真。
そんな豪真に心が魅かれ、十九歳で豪真と電撃結婚し、その一年後に彰を生んだ。
「終わったぞ」
「お疲れ」
外の暖かな夕日の光を浴びながら、仕事が終わった豪真が、車で理亜たちを迎えに来た。
理亜は感謝の気持ちを込め口にする。
「お~。アキラ~。パパ仕事終わったよ~」
「パアパ」
豪真が馬鹿親全開で、締まりのない顔で彰に近付いていくと、彰は満面の笑みでおぼつかない足取りで豪真の元に走り出すと、ギュッと彰を抱きしめる豪真。
どこにでもある温かい家族。
そんな人並みの幸せを味わう理亜は、二人が微笑ましく思い、ニヤニヤ笑う。
「よし、帰るか」
「うん」
彰を抱っこしたまま豪真がそう言うと、理亜も元気よく頷く。
帰宅後、すぐに夕飯の支度をした豪真。
理亜は料理以外の家事は出来るが、料理が致命的に駄目で、豪真が率先して料理をする事になったのだ。
彰もおかゆなどの食べやすい料理を食べ、とてもご満悦の様子だった。
「それにしてもあれからもう六年か。早かったようで短かったな」
「ほんと、色々あったよね」
しみじみとした過去の波を体に受ける様にして、黄昏る様に語る豪真と理亜。
クリプバを通して、理亜も豪真も色々学び、経験し、遣る瀬無い思いもしながら今がある。
そんな豪真を見て、何か心苦しそうな面持ちを感じ取ったのか、食べる箸を止め「これからも仲良く年、取っていこうね」と感謝の気持ちを込め、笑みで口にする。
すると、豪真は少し呆気に取られた。
誰よりも辛い経験をしているはずの理亜が、ここまで人に気を使うまでなった事に、自分が少し不甲斐なく感じた豪真。
「ああ。これからも夫婦円満でな」
豪真も笑みで返す。
それを見てホッとした理亜は箸を再び使い、「これ美味しいね。私も久しぶりにチャレンジしようかな?」と話を切り出すと、豪真は慌てながら「いやいや! 料理は私に任して、理亜はいつも通りでいい。ただ理亜と彰が笑顔であってくれるだけで良いんだぞ」と冷や汗を流しながら口にする。
実は、結婚当初、理亜が腕を振るって豪真に愛妻弁当を作ったのだが、食べ終え、診療所の患者の前で顔を青ざめ、お腹を押さえて倒れてしまった。
完全な食中毒。
それを体験した豪真は、理亜にどうして食中毒になったか詳細を口にせず、豪真が料理を喜んで振るう事になったのだ。


コメント