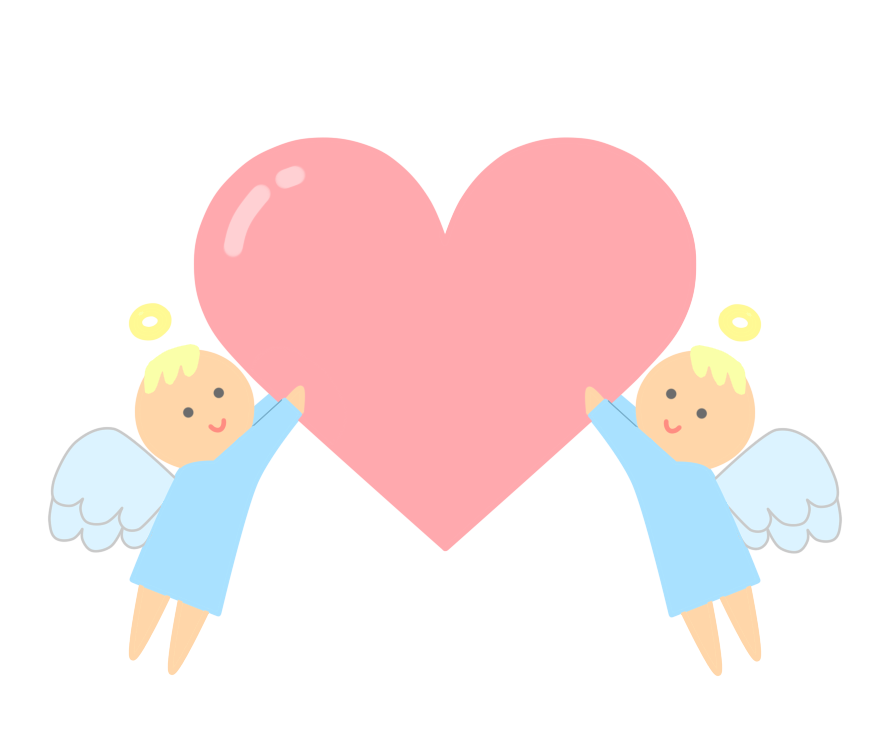
第五十二章 最高の思い出を君に届ける 六話
それから七カ月後、理亜がALSだと言う事は、少数の人間しか知らない。
奏根たちと、お世話になっていた輝美たち。
理亜は隠しきったまま、コンサートや野外ライブ、CDの販売で、根強い人気者になった。
そして、理亜が出した新曲、『いつまでも君の傍にいるよ』が世界中で大ヒットし、アメリカで、最優秀レコード賞を受賞した。
理亜はアメリカに行った時には、既に車椅子に乗っていた。
流石に何故、車椅子生活を送っている事を追及されれば、自然と「自分はALSに罹っています」とメディアの前で口にしてしまう他ない。
それを知った世界中は、理亜を称賛した。
闘病しながらも、ここまで天高く歩いてきたことに。
そして、理亜が世界中に足を運び、コンサートを終える頃には、完全に足腰の感覚は無くなり、介護なしでは生きていけない体になってしまう。
豪真はそんな理亜を目にしても、挫けず、それどころか、今日も頑張るぞ、と元気溌剌で接してくれる。
理亜は、本当に良い人を見つけたと、豪真との愛の絆を再確認した。
そして、理亜が砂川に帰省して、手足の痺れが酷くなってる事に気付く。
すると、理亜は、豪真に「最後の舞台、ここでしたいな」と等々、聞きたくなかった言葉を聞いてしまう。
豪真は涙を押し殺し、唇を噛み締めながら、無理やり笑顔になり「どこが良いんだ?」と聞いてきた。
そんな理亜が選んだ、最後の舞台場。
それは、クリーチャープレイバスケットボールの決勝戦の舞台のコートの上だった。
豪真は理亜らしいと思い、思わず素で笑ってしまう。
豪真はすぐに行動に移す。
もう、理亜に残されている時間は少ない。
持って一週間と言った所。
イベント主催者は管轄の警察署への事前相談が必要となっていたが、理亜の容態を聞いた砂川の警察署長だけでなく、砂川の市長も快く快諾してくれた。
理亜が決めてから四日後。
宣伝も殆どなかったと言うのに、会場は満員だった。
それどころか、世界中に理亜の演奏を届けようと、テレビカメラなども配置され、スタッフらでコートの周りの端は、埋め尽くされていた。
ライブ配信なため、理亜も緊張していた。
理亜は車椅子で豪真に押されながら会場に近付くと、昔、郁美に車椅子で背中から押されていた懐かしく暖かい思い出が、脳裏を過る。
「ほんと、不思議だね」
「ん? 何がだ?」
歩道を歩いていた豪真に、ふと話を振ってくる理亜に豪真は首を傾げる。
「最初に車椅子に乗せられてた時の私は、ただ片足がないだけのどこにでもいる女の子だったのに、今の車椅子生活とは大違い」
くすくす笑いながら喋る理亜に、豪真は「そうか? 私は昔のお前と、今のお前を比較しても何にも変わってない様に思えるぞ」と誇らしげに口にする。
「そうかな?」
「ああ。そうだ。いつまでたっても、人を魅了し、引き付ける。そんなお前は昔とちっとも変ってない」
大空を眺めながら、感傷に浸る様に、儚げに口にする豪真。
あの頃が懐かしい、と心の底から思ってしまう。
そんな黄昏ている時に、下校中の二人の小学五年生の、男子が、理亜に向かって、「無能だ! 無能が居る!」「車椅子で引かれてるとか、ダサッ」と悪口を向けて言って来る。
その顔を人を潮笑う、悪意そのものだった。
豪真は怒りが込み上がり、鋭い目で睨みつけ、思わず怒鳴りつけてやろうとしたその時。
「二足歩行がなんぼのもんじゃー!」
腹の底から不満を爆発させたのは理亜だった。
握り拳を作り、勇ましく口にする理亜。
すると、二人の男子学生は、そんな理亜を見て益々、馬鹿にするように笑い出す。
しかし、そこで天罰が下る。
なんと、走行している車が、その二人の男子学生の近くにあった水溜まりを通り、勢いよく、その水飛沫を顔から全体に浴びてしまったのだ。
「うえっ!」
「くさっ!」
汚水だったのか、かなり不快感を露わにしていた二人のガキんちょに、豪真と理亜は思わず笑ってしまい、さっさとその場を去った。


コメント